春のお彼岸シーズンになると、
カレンダーに書かれた「春分の日」の文字を
目にすることが増えますね。
でもふと考えてみると…
春分の日ってどんな日?
なぜ祝日なの?
どうしてお墓参りをするの?
そんな素朴な疑問を
抱いたことはありませんか?
今回は、春分の日の意味や由来、
お墓参りとの関係について
やさしくご紹介します。
春分の日とは?
春分の日は、国民の祝日のひとつです。
2024年の春分の日は3月20日(水)ですが、
毎年同じ日ではありません。
これは天文学的な現象に基づいて
決まっているからなんです。
昼と夜の長さがほぼ同じになる日
として知られています。
太陽が真東から昇り、真西に沈むことで
昼夜のバランスが取れる特別な1日です。
また、春分の日は二十四節気のひとつでもあり、
本格的な春の訪れを告げる節目の時期でもあります。
なぜ祝日なの?
春分の日が祝日である理由は、
法律にもきちんと書かれています。
「自然をたたえ、生物をいつくしむ」
というのが、春分の日に込められた意味です。
春分の日は自然や命に感謝する日とされています。
春は植物が芽吹き、動物も活発になる時期。
私たち人間も自然の恵みの中で生きている
ということを改めて感じられる日ですね。
だからこそ、ただ「お休みの日」としてではなく、
自然や命に思いを寄せる日として
過ごしたいですね。
春分の日にお墓参りをするのはなぜ?
春分の日と聞いて、
「お彼岸」を連想する方も
多いのではないでしょうか。
実はこの春分の日、
お彼岸の「中日(ちゅうにち)」に
あたる日なのです。
お彼岸とは、
日本独自の仏教的な風習で、
先祖を敬い供養する期間のことです。
春分の日をはさんで前後3日、
合計7日間が「春のお彼岸」と呼ばれ、
この期間にお墓参りをするのが
古くからの慣習となっています。
太陽が真西に沈むため、
ご先祖さまがいるとされる「西方極楽浄土」に
つながりやすい日と考えられてきました。
こうした理由から、
春分の日は「ご先祖に思いをはせる日」
ともいわれるようになったのです。
春分の日と秋分の日の違いは?
ちなみに、秋にも「秋分の日」がありますね。
この日もまた昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、
「秋のお彼岸」の中日でもあります。
では春と秋、何が違うのでしょうか?
| 項目 | 春分の日 | 秋分の日 |
|---|---|---|
| 時期 | 3月20日前後 | 9月23日前後 |
| 自然の変化 | 昼がだんだん長くなる | 夜がだんだん長くなる |
| 祝日の意味 | 自然と生命をたたえる | 祖先を敬い、しのぶ |
どちらも「自然と命に感謝する日」ですが、
春は芽吹きの季節、秋は実りの季節といった
季節感の違いがありますね。
太陽の動きが区切りになるため、
仏教だけでなく、古代からの自然信仰とも
結びつきの深い日といわれています。
だからこそ、お彼岸のお墓参りも
ただの習慣ではなく、
自然や先祖に感謝する
心の時間といえるのかもしれません。
春分の日はどう過ごす?
春分の日は、
自然や命に思いを向けるとともに、
心を整える日として
ゆっくり過ごしたいものです。
忙しい毎日の中では、
「ただの祝日」として
流してしまいがちかもしれません。
でも、春分の日は
自然のバランスが整う節目の日
ともいえます。
「昼」と「夜」が等しくなる日。
このバランスを、自分自身の心や暮らしにも
重ねてみてはいかがでしょうか🌱
たとえば、こんなふうに過ごすのもおすすめです。
✔ ご先祖への感謝をこめてお墓参り
✔ 春の花を飾って心を整える
✔ 一日だけでも、自然と触れ合う時間をつくる
どれも難しいことではありませんが、
「感謝の気持ち」を持つことで
春分の日の意味がグッと深まります。
あとがき
春分の日は、昼と夜が同じ長さになる
自然の節目の日であると同時に、
日本の文化や仏教の考え方とも深くつながった
心を整える1日です。
お墓参りを通してご先祖を敬い、
自然と命に感謝をするこの祝日。
せっかくのお休みだからこそ、
春のやさしい光の中で、
穏やかな気持ちで過ごしてみませんか。

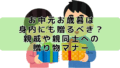
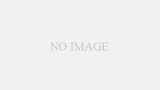
コメント