近年、取引先や顧客から「年賀状じまい」の案内を受け取る機会が増えてきました。
しかし、いざ通知を受け取ると「返信は必要なのか?」「どんな言葉を選べば良いのか」と迷ってしまいますよね。
この記事では、ビジネスシーンにおける年賀状じまいの基本マナーと、状況に応じてすぐに使える返信文例を丁寧にまとめました。
取引先や顧客、社内の上司・同僚など、相手ごとに適したフルバージョンの例文もご用意しています。
「これからも関係を大切にしたい」という気持ちを伝える一言が、年賀状じまいをきっかけに信頼を深めるカギになります。
この記事を通して、迷うことなく心のこもった返信ができるようになりましょう。
年賀状じまいとは?ビジネスでの背景と意味
ここでは「年賀状じまい」という考え方の意味と、なぜビジネスの現場でも広がっているのかを整理してみましょう。
背景を理解しておくと、返信の仕方にも納得感が生まれます。
なぜ年賀状じまいが広がっているのか
年賀状じまいとは「これからは年賀状でのやりとりを控えます」という意思表示のことです。
従来の年賀状文化が縮小してきた理由には、社会のデジタル化や働き方の多様化があります。
紙のやり取りからメールやSNSへ移行する人や企業が増えたことで、自然と年賀状じまいを選ぶ動きが目立つようになっています。
年賀状じまいは「疎遠になる」のではなく、「新しい方法で関係を保つための選択」なのです。
| 背景 | 広がった理由 |
|---|---|
| デジタル化 | メールやSNSでの挨拶が主流になった |
| 働き方の変化 | 在宅勤務などで年賀状作成の習慣が薄れた |
| 環境への配慮 | 紙の削減や印刷コストを抑える意識 |
企業や個人が選ぶ主な理由
企業が年賀状じまいを決める場合、よくある理由は「会社方針の変更」「デジタル化推進」「業務効率化」などです。
一方、個人では「年末年始の作業を減らしたい」「オンラインで挨拶するほうが自然」といった事情もあります。
大切なのは「やめます」ではなく「これからも別の形でご縁を大切にします」と伝える姿勢です。
そうした一言を添えることで、受け取る側も安心し、良好な関係を保ちやすくなります。
年賀状じまいを受け取った時の基本マナー
年賀状じまいの通知を受け取ると「どう返せばいいのだろう」と戸惑う方も多いはずです。
ここでは、返信が必要かどうかの判断基準や、返信を控えるべき場合のマナーについて整理していきます。
返信は必要?ケースごとの判断基準
年賀状じまいの案内が届いたとき、必ずしも返信しなければいけないわけではありません。
「今後は年賀状での挨拶を控えます」と明記されている場合、返信しなくても失礼にはあたりません。
ただし、長年の取引先や信頼関係を築いてきた相手に対しては、感謝の気持ちを伝える一言を返すとより丁寧です。
ビジネスでは「人間関係を大切にしている姿勢」を示すこと自体が大きな意味を持ちます。
| 状況 | 返信の要否 |
|---|---|
| 年賀状じまいの通知のみ | 必須ではない |
| 長年の取引先や大切な関係先 | 返信して感謝を伝えるのが望ましい |
| 社内の上司や同僚 | 簡単でも返信すると丁寧 |
返信を控えるべき場合とその配慮
案内の中に「返信はご無用です」と明記されている場合は、その言葉に従うのが礼儀です。
相手は「返事を気にしなくていいですよ」と配慮しているので、あえて返信すると負担をかける可能性があります。
相手の意思を尊重することが最も大切なマナーです。
ただし返信しない代わりに、次回の連絡や会話の中で感謝の一言を添えると、自然に気持ちを伝えられます。
例えば「先日はご丁寧なご連絡をありがとうございました」と一言加えるだけでも印象は変わります。
ビジネスで使える年賀状じまい返信文例集
ここでは、実際に使える返信文例を状況別にご紹介します。
取引先や顧客、社内など、相手やシーンごとに言葉を調整することで、より自然で丁寧な対応が可能になります。
全文をそのまま使えるフルバージョン例文も用意しましたので、用途に合わせてご活用ください。
取引先や業務パートナーへの文例
取引先や外部パートナーへの返信は、フォーマルさを大切にしつつ、今後も良好な関係を続けたい気持ちを込めましょう。
| ケース | 文例 |
|---|---|
| 一般的な返信(年賀状またはメール) | 拝啓 新春の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 このたびは年賀状を賜り、誠にありがとうございました。 また、今後のご対応についてご丁寧にお知らせいただき、重ねて御礼申し上げます。 これまで賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご交誼をお願い申し上げます。 敬具 |
| 「返信不要」と書かれていた場合 | 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 長年にわたり心温まる年賀状を頂戴し、厚く御礼申し上げます。 今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。 なお、ご配慮いただきました通り、本メールへのご返信は無用にてお願い申し上げます。 敬具 |
顧客・個人の取引先への文例
顧客や個人の取引先へは、少し柔らかい表現で、親しみと今後の関係を大切にしたい気持ちを伝えるのがおすすめです。
| ケース | 文例 |
|---|---|
| 顧客や個人向け | あけましておめでとうございます。 このたびはご丁寧なご挨拶をいただき、誠にありがとうございました。 また、年賀状じまいの件につきまして、承知いたしました。 これからも変わらぬご厚誼のほど、よろしくお願い申し上げます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
| 親しみを込めた簡易返信 | あけましておめでとうございます。 いつも温かいお気遣いをいただき、心より感謝いたします。 年賀状じまいの件、承知いたしました。 今後とも変わらずご縁を大切にしてまいりたく存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
社内(上司・同僚)への文例
社内でのやり取りは形式的でよいものの、感謝や敬意を伝える一言を入れると印象が良くなります。
| ケース | 文例 |
|---|---|
| 上司への返信 | あけましておめでとうございます。 旧年中は格別のご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。 年賀状じまいの件、承知いたしました。 本年も引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 |
| 同僚への返信 | あけましておめでとうございます。 ご丁寧なご挨拶をありがとうございました。 年賀状じまいの件、承知いたしました。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。 |
いずれのケースでも「これからも関係を大切にしたい」という一文を入れることが鍵です。
返信するときに気をつけたいポイント
年賀状じまいへの返信は、文例をそのまま使うだけでなく、送るタイミングや言葉選びに心を配ることで、より好印象につながります。
ここでは、返信時に押さえておきたい大切なポイントを整理しました。
送るタイミングと適切な方法
返信はできれば1月中、遅くとも立春(2月初旬)までに行うのが理想です。
形式は年賀状に限らず、メールや寒中見舞いでも問題ありません。
大切なのは「受け取ってすぐに対応した」という誠意を示すことです。
| 返信手段 | メリット |
|---|---|
| 手紙・はがき | フォーマルで丁寧な印象を与えられる |
| メール | すぐに送れるため、スピード感を示せる |
| 寒中見舞い | 1月下旬以降でも自然に送れる |
返信に盛り込みたい言葉やフレーズ
返信文には、相手への感謝や今後の関係を大切にする気持ちを必ず入れましょう。
以下のようなフレーズを取り入れると自然にまとまります。
- 「これまでのご厚情に感謝申し上げます」 → 長いお付き合いに感謝を伝える
- 「今後とも変わらぬご交誼をお願い申し上げます」 → 関係継続の意思を明示する
- 「ご配慮を賜りありがとうございます」 → 「返信不要」とあった場合に添えると丁寧
ただ事務的に「了解しました」と返すのではなく、温かみのある一文を足すことが大切です。
年賀状以外での今後の挨拶手段
年賀状じまいをきっかけに、今後はメールやオンラインでの挨拶へ移行するケースも増えています。
その場合は「今後はメールでご連絡させていただきます」など、次の手段を一言添えるとスムーズです。
「年賀状はやめる=交流の終わり」ではなく、「新しい方法でつながる」ことを意識しましょう。
| 手段 | おすすめの表現 |
|---|---|
| メール | 「今後はメールにてご挨拶させていただきます」 |
| SNS | 「これからはSNSでも近況をご報告させていただきます」 |
| 直接の会話 | 「今後はお目にかかる機会にご挨拶できれば幸いです」 |
年賀状じまいをきっかけに関係を深める工夫
年賀状じまいは「関係を終わらせる」ためではなく、「新しい形で関係を続ける」ための選択です。
ここでは、年賀状じまいをきっかけにして、むしろ関係をより良くする工夫について考えてみましょう。
ビジネス関係を円滑に保つための姿勢
年賀状がなくなることで形式的なやりとりは減りますが、その分、実際のコミュニケーションが重要になります。
例えば、取引先との定例連絡の中で「先日はご丁寧なご案内をいただき、ありがとうございました」と一言添えるだけでも印象は大きく変わります。
年賀状じまいの後は「相手を思い出したときに連絡を取る」柔軟さが、関係を深めるカギになります。
| 工夫 | 効果的な理由 |
|---|---|
| 定期的な近況メール | 形式に縛られず、必要なときに連絡できる |
| 対面やオンラインでの挨拶 | 直接言葉を交わすことで信頼が強まる |
| 季節の挨拶をメールで送る | 柔軟な対応ができ、相手の負担にならない |
自分が年賀状じまいをする場合の注意点
自分から年賀状じまいを伝えるときは、相手に「もう関係を持ちたくないのでは」と誤解されないよう注意が必要です。
「今後は別の方法でご挨拶をさせていただきます」といった前向きな言葉を添えるのがポイントです。
単に「やめます」と伝えるだけでは、冷たい印象を与えてしまうので避けましょう。
フルバージョンの例文としては、以下のような形がおすすめです。
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 このたび、年賀状でのご挨拶を控えさせていただくことといたしました。 これまで頂戴しました温かいお心遣いに、心より感謝申し上げます。 今後は折々の機会にメール等でご挨拶をさせていただきたく存じます。 引き続き変わらぬお付き合いを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 敬具
「今後も関係を続けたい」という意志を示すことで、年賀状じまいがむしろ信頼を深めるきっかけになります。
まとめ―心を込めた返信でビジネス関係をつなぐ
ここまで、年賀状じまいの背景や基本マナー、そして実際に使える文例をご紹介しました。
大切なのは「形式的に返す」ことではなく、「これからも関係を大切にしたい」という気持ちを伝えることです。
特にビジネスの場では、人との信頼関係が何よりの財産です。
年賀状じまいをきっかけに、より自然で負担の少ないコミュニケーションを築くことができます。
| 押さえておきたいポイント | 要点 |
|---|---|
| 返信の必要性 | 相手との関係性を見て柔軟に判断 |
| 返信の工夫 | 感謝と今後の関係継続を必ず伝える |
| 代替手段 | メールや直接の会話など、新しい方法に切り替える |
「返信は不要」とあった場合も、次の会話や別の場面で感謝を添えることで印象はぐっと良くなります。
年賀状じまいは時代の流れに沿った自然な変化です。
だからこそ、心を込めた一言を大切にし、これからのビジネス関係をより豊かなものにしていきましょう。

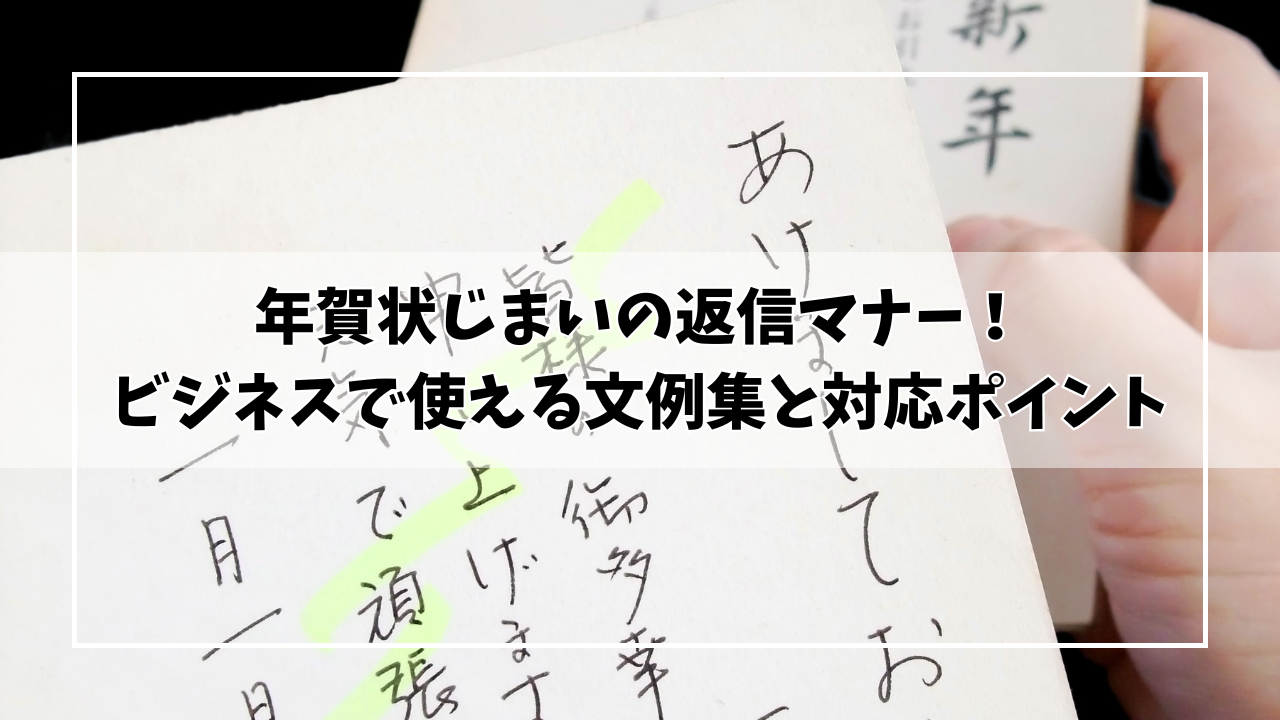
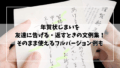
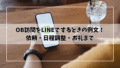
コメント