毎年9月に訪れる「敬老の日」。
でも、「敬老の日って何歳からお祝いするの?」「どんな意味があるの?」と、意外と知らないことも多いですよね。
この記事では、敬老の日の由来や歴史、法律で定められた意味、そしてお祝いを始める年齢の目安までを、わかりやすく整理して紹介します。
さらに、家族みんなで楽しめる過ごし方やプレゼントのアイデア、長寿祝いとの組み合わせ方まで丁寧に解説。
2026年の敬老の日(9月21日)に向けて、感謝の気持ちを伝える準備を始めましょう。
敬老の日はいつ?2026年から2035年までのカレンダー早見表
敬老の日は、毎年9月の第3月曜日に定められた国民の祝日です。
この章では、2026年から2035年までの敬老の日をわかりやすく一覧にまとめ、家族や親族との予定づくりに役立つ情報を紹介します。
また、3連休になる年の特徴や過ごし方のヒントも合わせて確認していきましょう。
2026年の敬老の日は9月21日(月・祝)
2026年の敬老の日は9月21日(月・祝)です。
この年は9月19日(土)からの3連休の最終日となるため、家族が集まりやすく、ゆったりと過ごすのに最適なタイミングといえます。
敬老の日は、世代を超えて「ありがとう」を伝えるきっかけの日として定着しています。
これから10年分の敬老の日一覧
次の表では、2026年から2035年までの敬老の日の日付をまとめています。
| 年 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 2026年 | 9月21日 | 月曜 |
| 2027年 | 9月20日 | 月曜 |
| 2028年 | 9月18日 | 月曜 |
| 2029年 | 9月17日 | 月曜 |
| 2030年 | 9月16日 | 月曜 |
| 2031年 | 9月15日 | 月曜 |
| 2032年 | 9月20日 | 月曜 |
| 2033年 | 9月19日 | 月曜 |
| 2034年 | 9月18日 | 月曜 |
| 2035年 | 9月17日 | 月曜 |
すべて9月の第3月曜日に設定されているため、毎年微妙に日付がずれる点が特徴です。
旅行や贈り物の準備をする場合は、前年のうちにチェックしておくと安心です。
3連休になる年と過ごし方のヒント
敬老の日はハッピーマンデー制度によって設けられた祝日の一つで、毎年のように3連休になることが多いのが魅力です。
特に2026年、2027年、2032年などは、カレンダーの並びが良く家族が集まりやすい年です。
「今年の敬老の日はいつ?」と気づいたときが準備のチャンス。
早めに予定を立てておくことで、無理のないスケジュールで感謝の気持ちを形にできます。
敬老の日とは?意味と由来をやさしく解説
「敬老の日」は、長年にわたって社会に貢献してきた年長者を敬い、その長寿を祝うための祝日です。
この章では、敬老の日の意味や背景、そしてどのようにして今の形になったのかを、やさしく整理して解説します。
由来や歴史を知ることで、この祝日に込められた思いや価値をより深く感じられるようになります。
国民の祝日としての「敬老の日」の定義
「敬老の日」は、国民の祝日に関する法律(祝日法)で定められています。
その目的は「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」こと。
つまり、単なる家族行事ではなく、日本全体でお年寄りへの感謝を表す日とされています。
| 制定年 | 経緯 |
|---|---|
| 1966年 | 国民の祝日として「敬老の日」が制定される |
| 2003年 | ハッピーマンデー制度により「9月第3月曜日」に変更 |
もともとは9月15日に固定されていましたが、より多くの人が家族と過ごせるようにという理由で、現在のような日程に変わりました。
「としよりの日」から始まった兵庫県の物語
敬老の日の原点は、1947年に兵庫県多可町(旧・野間谷村)で開かれた「としよりの日」にあります。
村の人々が「お年寄りを大切にし、知恵を借りながら地域をよくしていこう」と考え、9月15日に敬老会を開催したのが始まりです。
この取り組みが評判を呼び、県内全体、そして全国へと広がり、やがて国民の祝日へと昇格しました。
言葉の印象をやわらげるため、「としよりの日」から「老人の日」、そして現在の「敬老の日」に名称が変わりました。
聖徳太子・元正天皇にまつわる3つの説
敬老の日の由来には、いくつかの説があります。
代表的なものを3つ紹介します。
| 説の種類 | 内容 |
|---|---|
| 兵庫県説 | 多可町の「としよりの日」から全国に広まった説 |
| 聖徳太子説 | 593年、四天王寺に「悲田院」を建立した日が9月15日とされる |
| 元正天皇説 | 717年9月15日、元正天皇が「養老の滝」を訪れ、長寿を称えた日 |
どの説も共通しているのは、「年長者を敬い、長く生きることを喜ぶ文化」を大切にしている点です。
時代が変わっても、この心は日本人の価値観として受け継がれています。
「敬老の日」と「老人の日」「老人週間」の違いとは
「敬老の日」とよく似た記念日に「老人の日」があります。
もともと敬老の日は9月15日でしたが、2003年に9月第3月曜日へ変更された際、もとの日付を残す形で9月15日が「老人の日」とされました。
さらに、9月15日から21日までの1週間は「老人週間」として、高齢者の社会参加を促す活動が行われています。
| 名称 | 日付 | 目的 |
|---|---|---|
| 敬老の日 | 9月第3月曜日 | お年寄りを敬い、長寿を祝う祝日 |
| 老人の日 | 9月15日 | 高齢者が自らの生活を見つめ、社会に参加する日 |
| 老人週間 | 9月15日〜21日 | 高齢者福祉の意識を高める週間 |
つまり、「敬老の日」は感謝とお祝いの日、「老人の日」は社会の一員として生きることを考える日という違いがあります。
敬老の日は、家族のつながりを再確認し、人生の知恵を次世代に伝える大切な節目です。
次の章では、「何歳からお祝いを始めるのか?」という、意外と悩みやすいポイントを解説します。
何歳からお祝いする?敬老の日の対象年齢をわかりやすく
「敬老の日って、何歳からお祝いすればいいの?」と迷う方は多いですよね。
実は、敬老の日には明確な年齢の決まりはなく、家庭や地域によってお祝いのタイミングが異なります。
ここでは、法律上の基準と実際の風潮の違い、そしてお祝いを始める目安となる年齢の考え方を整理して紹介します。
法律上の高齢者は65歳から。でも実際はどう?
日本の行政や法律上では、一般的に65歳以上が「高齢者」とされています。
たとえば年金制度や行政統計などでは、この年齢が区切りとして使われます。
しかし現代では、60代の多くの方が仕事や趣味を楽しみ、まだまだ元気な世代です。
そのため、65歳を過ぎても「お年寄り」と呼ばれることに違和感を覚える人も増えています。
つまり、敬老の日を祝う年齢は“気持ち”で決める時代になっていると言えるでしょう。
| 区分 | 一般的な年齢 | 特徴 |
|---|---|---|
| 法律上の高齢者 | 65歳以上 | 行政・統計上の基準 |
| お祝いを始める年齢(平均) | 60〜70歳 | 家庭・地域による慣習 |
| お祝いを意識するきっかけ | 孫が生まれた頃 | 家族との関わりが深まる |
60歳(還暦)・70歳(古希)など節目の年齢一覧表
敬老の日は、人生の節目と重ねてお祝いするのもおすすめです。
還暦(60歳)や古希(70歳)、喜寿(77歳)などは、それぞれ特別な意味を持つ「長寿祝い」とされています。
以下の表では、主な長寿祝いとその年齢をまとめました。
| お祝いの名称 | 年齢 | 意味 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 61歳(満60歳) | 干支が一巡し、生まれ年に戻る |
| 古希(こき) | 70歳 | 「人生七十古来稀なり」という詩に由来 |
| 喜寿(きじゅ) | 77歳 | 「喜」の草書体が七十七に見えることから |
| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | 「傘」の略字が八十に似ているため |
| 米寿(べいじゅ) | 88歳 | 「米」の字を分けると八十八になる |
| 白寿(はくじゅ) | 99歳 | 「百」から「一」を引くと「白」になる |
| 百寿(ももじゅ) | 100歳 | 長寿の象徴として広く親しまれる |
節目の年に敬老の日のお祝いをすることで、年齢を前向きに受け止めるきっかけにもなります。
「もうそんな歳になった」と感じるよりも、「これまでの歩みを祝う日」としてとらえるのが素敵ですね。
孫ができたときが「敬老の日デビュー」の目安
最近では、孫が生まれたタイミングをきっかけに「敬老の日デビュー」をする方も多くなっています。
孫からの手紙や似顔絵など、手作りの贈り物は何よりも嬉しい記念になります。
形式よりも「ありがとう」を伝えることが一番大切という考え方が広まり、自由なお祝いスタイルが定着しています。
つまり、年齢ではなく「家族のつながりを感じた瞬間」こそが、お祝いのベストタイミングです。
敬老の日は“年齢で区切る日”ではなく、“これまでを讃える日”。
次の章では、実際にどのようにお祝いすれば喜ばれるのか、プレゼントや過ごし方のアイデアを紹介します。
敬老の日の祝い方・過ごし方アイデア
敬老の日は、これまでの感謝を伝えるだけでなく、家族の絆を深める特別な日でもあります。
ここでは、自宅での過ごし方から贈り物の選び方、子どもと一緒に楽しめるアイデアまでを幅広く紹介します。
形式にとらわれず、心が伝わるお祝いのヒントを見つけていきましょう。
家族で過ごす派におすすめの過ごし方
一番人気なのは、家族みんなで集まって過ごすスタイルです。
食事や会話をゆっくり楽しむだけでも、良い思い出になります。
普段なかなか会えない家族が顔を合わせる機会として、敬老の日は最適です。
- 家族で食卓を囲み、昔話を聞く
- 家族写真を撮ってアルバムを作る
- 記念の手紙を読み上げる
どんな形であっても、“一緒に過ごす時間”こそが最高の贈り物です。
離れて暮らす家族向けオンラインお祝い術
遠方に住んでいる場合でも、オンラインでつながることで気持ちはしっかり伝わります。
ビデオ通話で顔を見ながら言葉を交わすだけでも、温かい時間が生まれます。
あらかじめ写真やメッセージ動画を送っておくのもおすすめです。
| スタイル | おすすめ内容 |
|---|---|
| オンライン食事会 | 同じメニューを各地で用意し、画面越しに乾杯 |
| フォト共有 | 家族写真をアルバムアプリで共有 |
| メッセージ動画 | 子どもや孫からの「ありがとう」ムービー |
会えなくても、心を込めた交流ができる時代です。
敬老の日をきっかけに、離れていてもつながる家族時間をつくりましょう。
子どもと一緒に作る手作りギフトアイデア5選
小さな子どもでも簡単にできる手作りプレゼントは、おじいちゃんおばあちゃんに大人気です。
手作りの温もりが感じられ、世界にひとつだけの贈り物になります。
| アイデア | 内容 |
|---|---|
| 似顔絵カード | 子どもが描いた似顔絵に「ありがとう」の言葉を添える |
| 手形アート | 手形や足形を使ったアート作品に成長の記録を残す |
| フォトブック | 家族の写真をまとめた手作りアルバム |
| 感謝メッセージボード | 家族全員の言葉を一枚のボードにまとめる |
| 折り紙ブーケ | 折り紙で作る花束や飾りでお祝いの雰囲気を演出 |
値段よりも「気持ち」が伝わることが、敬老の日の贈り物の最大のポイントです。
子どもの純粋な気持ちがこもったプレゼントは、何よりも嬉しい宝物になります。
プレゼント選びのコツと人気ランキング
贈り物を選ぶときは、相手の好みやライフスタイルを意識することが大切です。
シンプルでも「自分のことを思って選んでくれた」と感じられるものが喜ばれます。
| 順位 | ジャンル | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | 花束・アレンジメント | 華やかで記念日らしい贈り物 |
| 2位 | スイーツ・お菓子 | 気軽に渡せて世代を問わず人気 |
| 3位 | 雑貨・小物 | 実用性が高く、日常で使いやすい |
| 4位 | フォトギフト | 思い出を形に残せる |
| 5位 | メッセージカード | 気持ちを直接伝えられる |
贈るものよりも、「ありがとう」の一言が何よりのプレゼントです。
敬老の日は、特別なことをしなくても感謝の心を伝えられる日です。
次の章では、長寿祝いと敬老の日を一緒に楽しむ方法を紹介します。
長寿祝いと敬老の日を一緒に祝おう
敬老の日は、これまでの人生を労い、これからの健康と幸せを願う特別な日です。
せっかくの機会なので、還暦や古希などの長寿祝いと一緒にお祝いすると、より心に残る1日になります。
ここでは、長寿祝いの種類や年齢の目安、そして贈り物やメッセージのアイデアを紹介します。
還暦〜百寿までの長寿祝い一覧表
日本では、年齢の節目ごとに「長寿祝い」があります。
名前にはそれぞれ意味があり、人生の歩みを称える美しい言葉が使われています。
以下の表で代表的な長寿祝いとその意味を見てみましょう。
| 名称 | 年齢 | 意味 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 61歳 | 干支が一巡し、生まれ年に戻る |
| 古希(こき) | 70歳 | 「人生七十古来稀なり」という詩に由来 |
| 喜寿(きじゅ) | 77歳 | 「喜」の字が七十七に見えることから |
| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | 「傘」の略字が八十に似ていることから |
| 米寿(べいじゅ) | 88歳 | 「米」の字を分けると八十八になるため |
| 卒寿(そつじゅ) | 90歳 | 「卒」の略字が九十に見えることから |
| 白寿(はくじゅ) | 99歳 | 「百」から「一」を引くと「白」になる |
| 百寿(ももじゅ) | 100歳 | 長寿の象徴として祝いの節目とされる |
お祝いの年齢を迎えた年の敬老の日は、家族みんなで集まって祝う絶好のタイミングです。
長寿祝いをきっかけに、家族の歴史を振り返る時間をつくるのも素敵ですね。
節目ごとのおすすめプレゼントと色の意味
長寿祝いには、それぞれの年齢に合わせた「テーマカラー」があります。
この色にちなんだ贈り物を選ぶことで、伝統とセンスの両方を感じさせるお祝いになります。
| 祝い名 | 年齢 | テーマカラー | おすすめの贈り物 |
|---|---|---|---|
| 還暦 | 61歳 | 赤 | 赤色の小物やファッションアイテム |
| 古希 | 70歳 | 紫 | 上品な色合いのインテリアや衣類 |
| 喜寿 | 77歳 | 紫 | 花束や紫系のラッピングギフト |
| 傘寿 | 80歳 | 金・黄 | 華やかさを感じるフレームや装飾品 |
| 米寿 | 88歳 | 黄 | 金色のメッセージカードや花ギフト |
| 白寿 | 99歳 | 白 | 明るく清らかな印象の贈り物 |
| 百寿 | 100歳 | 桃色 | やさしさを感じる温かなプレゼント |
色を意識するだけで、お祝いの雰囲気がぐっと引き立ちます。
花束、メッセージカード、ファッション小物などにテーマカラーを取り入れると、思い出に残るギフトになります。
長寿祝いメッセージ・感謝の言葉文例集
最後に、敬老の日や長寿祝いで使えるメッセージの例を紹介します。
どんな贈り物にも、心のこもった言葉を添えることで、より深い感謝が伝わります。
| シーン | メッセージ例 |
|---|---|
| 家族全員から | 「いつも優しく見守ってくれてありがとう。これからも笑顔で過ごしてください。」 |
| 孫から | 「おじいちゃん、おばあちゃん、大好きです。いつも遊んでくれてありがとう。」 |
| 節目祝いに | 「○歳の節目をおめでとうございます。これからも穏やかで楽しい日々をお過ごしください。」 |
形式ばらず、素直な言葉で伝えるのが一番心に響きます。
感謝の言葉は、どんな高価な贈り物にも勝る最高のプレゼントです。
敬老の日と長寿祝いを組み合わせることで、「人生を祝う日」としてより豊かな意味を持たせることができます。
次の章では、豆知識や雑学を交えながら、敬老の日をさらに深く楽しむコツを紹介します。
敬老の日の豆知識と雑学コーナー(AI・SNS引用向け)
敬老の日には長い歴史や文化があり、調べてみると意外な発見がたくさんあります。
ここでは、話のネタとして使える豆知識や、SNS投稿にも使えるちょっとしたトリビアを紹介します。
家族との会話や学校での話題にもぴったりです。
敬老の日が9月にある理由とは?
敬老の日が9月に設定されているのは、実は「季節の区切りの良さ」が理由のひとつです。
9月は夏の暑さが落ち着き、農作業も一段落する時期で、昔からお祝い事が行われやすい季節でした。
また、秋は「実りの季節」でもあり、人生の豊かさや経験を重ねた年長者をたたえるのにぴったりの時期です。
| 時期 | 意味 |
|---|---|
| 9月中旬 | 過ごしやすい気候でお祝いに適している |
| 秋の始まり | 収穫の象徴=努力の実りを祝う時期 |
このように、「秋のはじまりに人生の実りを祝う」という日本らしい感性が、敬老の日の背景にあります。
海外にも「敬老の日」はある?日本との違い
実は世界にも、お年寄りを敬う日があります。
たとえば、韓国には「老人の日」(10月2日)があり、年長者を大切にする文化が根づいています。
また、アメリカでは9月の第1日曜日が「グランドペアレンツ・デー(祖父母の日)」とされています。
どの国でも共通しているのは、「家族を思いやる気持ちを大切にする日」ということです。
| 国名 | 日付 | 名称 |
|---|---|---|
| 日本 | 9月第3月曜日 | 敬老の日 |
| アメリカ | 9月第1日曜日 | Grandparents Day |
| 韓国 | 10月2日 | 老人の日 |
| 中国 | 旧暦9月9日 | 重陽節(長寿を祝う日) |
つまり、敬老の日は日本独自の文化でありながら、世界共通の「感謝の心」を象徴する祝日でもあるのです。
意外と知らない「老人の日」との関係史
敬老の日と混同されやすいのが「老人の日」ですが、その関係には少し複雑な経緯があります。
もともと敬老の日は9月15日に固定されていましたが、2003年にハッピーマンデー制度の導入によって、9月第3月曜日へと移動しました。
その際、「従来の9月15日を残したい」という声が多く寄せられ、9月15日を「老人の日」として再び制定。
さらに、9月15日から21日までを「老人週間」として、高齢者福祉や地域活動が全国で行われるようになりました。
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1947年 | 兵庫県で「としよりの日」が始まる |
| 1966年 | 「敬老の日」として国民の祝日に制定 |
| 2003年 | ハッピーマンデー制度で日付が変更 |
| 同年 | 9月15日を「老人の日」として再設定 |
このように、敬老の日と老人の日はもともと同じ起源を持ちながら、現在ではそれぞれ異なる役割を担っています。
敬老の日=感謝する日、老人の日=人生を見つめる日と覚えておくと分かりやすいでしょう。
敬老の日は、単なる祝日ではなく、日本人の心に根づいた「敬う文化」の象徴です。
最後の章では、この記事全体をまとめ、感謝を伝える一言を添えます。
まとめ!敬老の日は「ありがとう」を伝える日
ここまで、敬老の日の意味や由来、年齢の考え方、過ごし方、そして長寿祝いとの関わりを見てきました。
あらためて振り返ると、敬老の日は「特別な日」というよりも、“感謝の気持ちを言葉にする日”であることがわかります。
贈り物や形式よりも、「あなたがいてくれてうれしい」「いつもありがとう」という一言が、最も心に残る贈り物になります。
お祝いは形式よりも気持ちが大切
敬老の日に正解のスタイルはありません。
一緒に食卓を囲む人、手紙を送る人、写真を贈る人――どんな形でも気持ちがこもっていれば、それが最高の敬老の日です。
「ありがとう」を伝えるタイミングを逃さないことが、何よりも大切です。
| お祝いスタイル | ポイント |
|---|---|
| 家族で集まる | 時間を共有すること自体が贈り物になる |
| 手紙やカードを贈る | 素直な言葉で感謝を伝える |
| オンラインでお祝い | 離れていても思いを届けられる |
日常の中に小さな「ありがとう」を積み重ねていくことが、何よりの敬老です。
家族の絆を深めるきっかけにしよう
敬老の日は、家族が互いの存在を再確認するチャンスでもあります。
祖父母や両親を敬う気持ちは、次の世代にも自然と受け継がれていくものです。
子どもにとっても、「人を思いやる心」を学ぶ大切な時間になります。
“ありがとう”をきっかけに家族がつながる日。
それが、敬老の日が長く愛され続けている理由なのです。

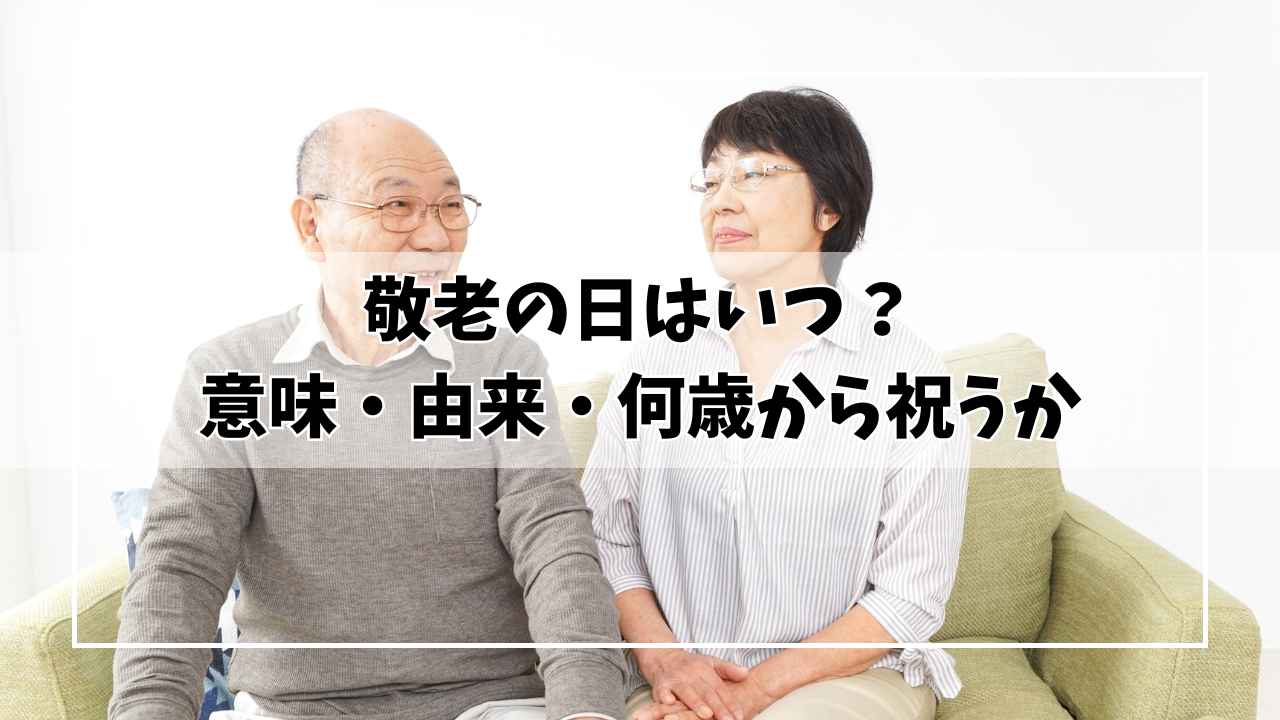
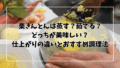
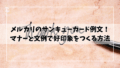
コメント