こんにちは。
中学校の生徒会選挙は、自分の思いを言葉にして伝える大切な機会ですよね。
しかし、「どんな演説をしたら伝わるのか」「何を話せば良いかわからない」と悩む人も多いはずです。
この記事では、2025年最新版の生徒会演説のトレンドや構成の作り方、そしてそのまま使える演説例文を紹介します。
立候補を考えている中学生の皆さんが、自信を持ってステージに立てるように、わかりやすく丁寧に解説しています。
この記事を読めば、「伝わる」「共感される」「印象に残る」演説が作れるようになります。
ぜひ、自分らしい言葉で、あなたの思いを学校中に届けましょう。
生徒会演説とは?中学生が知っておくべき基本
中学校の生徒会演説は、単に「立候補のあいさつ」をするだけの場ではありません。
自分の考えや学校への想いを、多くの生徒に伝えるための大切なチャンスです。
この章では、生徒会演説の目的や役割、そして聞き手が注目しているポイントをわかりやすく解説します。
生徒会演説の目的と役割
生徒会演説の目的は、自分の意見を発表することではなく、「みんなに信頼されるリーダー」としての姿勢を見せることにあります。
選挙は競争のように見えますが、本質は「より良い学校づくりを一緒に考える仲間を増やすこと」です。
そのため、演説では自分がどんな思いで立候補したのか、学校をどうしたいのかをしっかり伝えることが大切です。
たとえば、「学校をもっと笑顔のあふれる場所にしたい」「誰もが安心して意見を言える環境を作りたい」といった、聞く人がイメージしやすいメッセージを盛り込むと効果的です。
| 要素 | 内容例 |
|---|---|
| 目的 | 学校全体の雰囲気をより良くする提案を共有すること |
| 話す内容 | 自分の思い・提案・これまでの取り組み |
| 目標 | 「信頼できる」と思ってもらうこと |
演説を通して自分の熱意や誠実さを伝えることで、「この人なら任せられる」と感じてもらえるようになります。
聞き手が注目するポイント
聞いている生徒たちは、立候補者の言葉だけでなく、表情や声のトーン、姿勢などからも印象を受け取ります。
そのため、内容だけでなく話す態度や雰囲気もとても重要です。
特に注目されるのは次の3点です。
| 注目ポイント | 理由 |
|---|---|
| 話し方 | 自信と誠実さが伝わるテンポや声の大きさかどうか |
| 目線 | 聴衆と目を合わせて話せているか |
| 内容のわかりやすさ | 難しい言葉を使わず、具体的に説明できているか |
つまり、生徒会演説では「何を言うか」と同じくらい「どう言うか」も大事なのです。
あなたの言葉で伝える熱意こそが、一番の説得力になります。
2025年の生徒会演説トレンド
2025年の中学校生徒会選挙では、「個性」「多様性」「社会性」の3つが大きなキーワードになっています。
近年、学校でもSDGs(持続可能な開発目標)や地域連携など、社会に目を向けた活動が増えており、生徒会でもそうしたテーマが重視されるようになりました。
この章では、最新の演説テーマと話し方の傾向を紹介します。
人気のテーマとキーワード
2025年の生徒会演説では、次のようなテーマが特に注目されています。
| テーマ | 内容例 |
|---|---|
| みんなが意見を言いやすい学校 | 「意見箱」や「意見共有会」を通じて生徒の声を集める提案 |
| SDGs・環境にやさしい活動 | リサイクル活動や紙の節約など、身近にできる取り組み |
| 地域・他学年とのつながり | 交流イベントや異学年プロジェクトなど |
| 学校行事の活性化 | 文化祭・体育祭をもっとみんなで楽しむ工夫 |
| 自分らしさ・多様性の尊重 | 一人ひとりの得意を活かす場を増やす |
これらのテーマに共通しているのは、「みんなで学校をより良くする」という姿勢です。
自分だけでなく、全員が参加できる仕組みを提案することが支持されるポイントになっています。
最近の演説スタイルと話し方の傾向
かつての演説では、堅い言葉を使って「真面目さ」をアピールするケースが多くありました。
しかし最近は、同級生に話しかけるような自然な口調で、親しみやすく話すスタイルが主流になっています。
たとえば、「みなさんと一緒に考えていきたいと思います」や「私もまだまだ成長途中ですが」というように、謙虚さと協調性を示す表現が好印象を与えます。
| 話し方スタイル | 特徴 |
|---|---|
| 自然で会話的 | フレンドリーに感じられ、共感を得やすい |
| 前向きで明るい | 聞いている人の気持ちを明るくする |
| 短くわかりやすい | 時間内で要点をしっかり伝えられる |
また、オンライン発表や動画での演説が導入される学校も増えており、視線の向け方や声のトーンにも工夫が求められています。
つまり、これからの生徒会演説は「伝える力」だけでなく人に響く表現力が大切な時代になっているのです。
SNS・AI時代に評価される「誠実さ」の伝え方
情報がすぐに共有される今、派手な言葉よりも、正直で一貫性のあるメッセージが信頼を生みます。
たとえば、「自分ができることから始めたい」「小さな一歩をみんなで積み重ねたい」といった言葉は、等身大で共感を得やすい表現です。
誠実さや協調性を重視した演説こそ、2025年のトレンドの中心といえるでしょう。
効果的な演説原稿の作り方
生徒会選挙で印象に残る演説をするためには、内容の構成や言葉の選び方がとても大切です。
どんなに良いアイデアを持っていても、伝え方を間違えると聞き手には届きません。
この章では、演説原稿をつくる基本ステップと、わかりやすく魅力的に仕上げるためのコツを紹介します。
「導入・提案・締めくくり」三部構成の基本
演説原稿は、次の3つのパートで構成するとバランスが良くなります。
| 構成 | 内容のポイント |
|---|---|
| 導入(はじめ) | 自己紹介と立候補の理由を簡潔に伝える。「なぜ生徒会に入りたいのか」を明確にする。 |
| 提案(なか) | 学校をより良くするための具体的な取り組みを説明。共感や実現性を意識する。 |
| 締めくくり(おわり) | 全員への呼びかけと感謝の言葉でまとめる。「一緒にやっていこう」という前向きな締め方が効果的。 |
この三部構成を意識することで、聴く人が理解しやすく、説得力のある演説に仕上がります。
導入では短く印象を与え、提案部分では具体的な内容を盛り込み、最後は温かいメッセージで締めましょう。
印象に残るフレーズを作る方法
演説で聞く人の心をつかむためには、フレーズ選びにも工夫が必要です。
長い説明よりも、短くて覚えやすい言葉を使うと印象が残ります。
たとえば次のような表現は、自然で共感を得やすいです。
| 目的 | 効果的なフレーズ例 |
|---|---|
| みんなで協力したい | 「一人の力ではできないことも、みんなならできると思います。」 |
| 前向きな姿勢を伝える | 「小さなことから少しずつ、みんなで変えていきたいです。」 |
| 共感を呼びたい | 「私もみなさんと同じように、もっと学校を良くしたいと思っています。」 |
また、難しい言葉や抽象的な表現を避け、誰でも理解できる言葉を使いましょう。
聞く人の心に残るのは、立派な言葉よりも“自分の気持ち”です。
時間配分とリズムの作り方
生徒会演説は、通常2〜3分でまとめるのが理想です。
長すぎると集中力が切れてしまい、短すぎると内容が浅くなってしまいます。
おすすめの時間配分は次の通りです。
| パート | 時間目安 |
|---|---|
| 導入(自己紹介・立候補理由) | 約30秒 |
| 提案(取り組み内容) | 約1分30秒〜2分 |
| 締めくくり(呼びかけ・感謝) | 約30秒 |
さらに、リズムを意識することで聴きやすくなります。
1文を短く区切り、ゆっくりと話すことで、内容がしっかり伝わります。
特に大事な部分では間を取ると、聞き手の印象に残りやすくなります。
“早口よりも、心を込めた一言”のほうが強い印象を残します。
中学校生徒会演説の例文集【2025年最新版】
ここでは、実際に使える演説原稿をタイプ別に紹介します。
短い例文からそのまま使えるフルバージョンまで幅広く掲載しているので、自分の目的や性格に合ったものを選んで参考にしてください。
① 汎用型(まじめで誠実な印象を与える)
「みなさん、こんにちは。○年○組の○○○○です。私は今回、生徒会に立候補しました。
私は普段の学校生活の中で、もっとみんなが意見を出し合える場があったらいいなと感じていました。
そのため、毎月の学年集会などで、みんなの声を集める仕組みを提案したいと思います。
小さな声でも大切にできる学校にするために、私自身がその“きっかけ”になりたいです。
一緒に学校をより良くしていきましょう。どうぞよろしくお願いします。」
| 特徴 | 真面目で信頼感を与える内容。初めての立候補にもおすすめ。 |
|---|---|
| 時間目安 | 約2分 |
② 学校生活改善型(行事・ルールを良くしたい人向け)
「みなさん、こんにちは。○年○組の○○です。
私は学校を“もっと楽しく、もっと過ごしやすい場所”にしたいと思い、立候補しました。
特に文化祭や体育祭などの学校行事を、もっと生徒全員で協力して盛り上げられるようにしたいです。
そのために、事前にみんなの意見を集めて、行事のテーマや運営方法を一緒に決める仕組みを考えています。
行事を“先生が作るもの”ではなく、“みんなで作るもの”に変えていきたいです。
どうぞ応援をよろしくお願いします。」
| 特徴 | 活動的でリーダーシップを感じさせる内容。実行力をアピールしたい人に適しています。 |
|---|
③ SDGs・環境テーマ型(トレンドを意識した内容)
「こんにちは。○年○組の○○です。
私は、みんなが少しずつ“環境を考える学校”を目指して、生徒会に立候補しました。
たとえば、教室で使う紙を減らす工夫や、リサイクルボックスの設置など、すぐにできる取り組みを提案したいです。
また、ポスターや掲示物などを通して、みんなが自然に意識できるようにしたいと思います。
地球にやさしい学校を、みんなと一緒につくっていきましょう。よろしくお願いします。」
| 特徴 | 社会的な意識が高く、現代的な印象を与える。2025年のトレンドにも合致。 |
|---|
④ 個性・ユーモア型(印象に残るタイプ)
「こんにちは。○年○組の○○です。
私は“ちょっと変わった生徒会”を目指しています。
たとえば、朝のあいさつ運動をもっと楽しくするために、曜日ごとにテーマを決めたり、ちょっとしたクイズを出したりしてみたいです。
学校を“楽しい空間”に変えることで、自然とみんなの仲も深まると思います。
“笑顔の多い学校”を一緒に作っていけたらうれしいです。応援よろしくお願いします。」
| 特徴 | 個性を出したい人に最適。明るく覚えやすいスピーチ。 |
|---|
⑤ 感動・共感型(人の心を動かす演説)
「みなさん、こんにちは。○年○組の○○です。
私は、去年の学校行事でクラスのみんなが協力して成功させた瞬間を今でも忘れられません。
そのとき感じた“みんなで力を合わせる楽しさ”を、もっと学校全体で味わいたいと思いました。
そのために、学年やクラスを超えて協力できる行事を増やしたいです。
一人ひとりの力をつなげて、大きな成果を作る学校にしていきましょう。
どうぞ応援をよろしくお願いします。」
| 特徴 | 体験に基づいたエピソードで共感を呼ぶタイプ。聴衆の心に響く。 |
|---|
⑥ フルバージョン例文(そのまま使える完成形)
「みなさん、こんにちは。○年○組の○○○○です。私は今回、生徒会副会長に立候補しました。
私はこれまで、委員会活動や学校行事を通して、みんなで協力する大切さを感じてきました。
その中で、“もっとみんなが意見を言いやすい学校にしたい”という思いが強くなり、今回の立候補を決意しました。
私が目指すのは、『自分の意見を安心して話せる学校』です。
そのために、月に一度“生徒の声の日”を設け、クラスや委員会で出た意見を共有する場を作りたいと考えています。
また、その意見を生徒会でまとめて、先生方に提案する形を作ることで、より良い学校づくりにつなげていきます。
一人の意見が、学校全体を動かすきっかけになる。そんな学校を目指したいです。
私は完璧な人間ではありませんが、みんなと協力しながら、より良い学校を作るために全力を尽くします。
みなさんの一票で、学校を少しずつ変えていきましょう。どうぞよろしくお願いします。」
| 特徴 | 立候補理由・提案・呼びかけの三部構成が明確。模範的な演説全文。 |
|---|---|
| 時間目安 | 約3分30秒 |
この例文集をもとに、自分の言葉に少しアレンジすることで、より自然で伝わる演説になります。
演説を成功させる実践のコツ
せっかく一生懸命に作った演説原稿も、本番で緊張して伝えられなければもったいないですよね。
この章では、演説を実際に成功へ導くための準備と、当日の話し方・態度のポイントを解説します。
ちょっとしたコツを知るだけで、自信を持って堂々と話せるようになります。
緊張を和らげる準備方法
ほとんどの人が、演説の本番では緊張します。
しかし、緊張は「失敗のもと」ではなく「集中のサイン」と考えると、気持ちが少し楽になります。
まずは、自分の原稿を何度も声に出して練習しましょう。
鏡の前や家族の前で話すと、姿勢や声の出し方の確認にもなります。
| 準備のコツ | 具体的な方法 |
|---|---|
| リハーサル | 2〜3回以上、本番のスピードで通して練習する |
| 想定練習 | 教室や体育館など、人前に立つ環境で練習してみる |
| ポジティブ思考 | 「うまく話す」より「伝えたいことを話す」と意識を変える |
また、話す直前に深呼吸をゆっくり3回ほど行うと、心が落ち着きます。
緊張は悪いことではなく、むしろ真剣に話そうとしている証拠です。
話し方・目線・姿勢のポイント
演説の印象は、内容だけでなく話し方でも大きく変わります。
自信のある声で話すと、聴衆は自然と「この人の話を聞きたい」と感じます。
| 要素 | コツ |
|---|---|
| 声の出し方 | 少し大きめの声で、はっきりと話す。語尾を伸ばさず、キリッと締める。 |
| 目線 | 会場の3か所(中央・左・右)に順に視線を向けると、全員と話している印象を与えられる。 |
| 姿勢 | 背筋をまっすぐに伸ばし、胸を開くように立つと声が通りやすい。 |
また、手の動きを使って自然に表現することも効果的です。
大きな動きは不要ですが、ポイントを伝えるときに軽く手を動かすと、話にリズムが生まれます。
“姿勢・目線・声”の3つを意識するだけで、印象は驚くほど変わります。
演説後に意識したいフォロー
演説が終わったあとも、大切な時間が続きます。
立候補者としての印象は、演説だけでなくその後の行動でも決まります。
たとえば、他の候補者の演説をしっかり聞いたり、協力的な態度を見せたりすることで、「この人は信頼できる」と思ってもらえます。
| 演説後の行動 | 良い印象につながるポイント |
|---|---|
| 他の候補を応援する姿勢 | 公平で協調性のある印象を与える |
| 友達への感謝 | 支えてくれた人にお礼を伝えると信頼度が上がる |
| 落ち着いた態度 | 結果に関わらず、冷静な姿勢を保つことが大切 |
演説は「言葉で伝える」場ですが、その後の行動こそが本当の評価につながります。
“演説が終わってからが、本当のスタート”という意識を持つことが成功の秘訣です。
まとめ:伝わる演説は「共感+具体性」で決まる
中学校の生徒会演説は、単なる自己紹介や立候補のあいさつではありません。
聞いている生徒一人ひとりの心に、「この人と一緒に学校を良くしたい」と思ってもらうことが目的です。
そのためには、内容を「共感」と「具体性」の2つで支えることが大切です。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 共感 | みんなが感じている課題や気持ちに寄り添う。自分の思いを押しつけない。 |
| 具体性 | 「何をどう変えたいのか」をはっきり伝える。実現できそうな提案を入れる。 |
また、原稿を作る段階では「どんな学校にしたいのか」をイメージしながら言葉を選ぶと、演説全体に一貫性が出ます。
ただ上手に話すだけではなく、真剣に考えた言葉が人の心を動かすということを、ぜひ覚えておきましょう。
演説の上手さよりも、思いの強さが伝わることが一番の成功です。
そして、演説が終わってからも、その思いを行動で示していくことが、本当のリーダーへの第一歩です。
あなたの言葉が、学校を少しずつ変えていくきっかけになる。
このページの例文やポイントを参考に、自分の言葉で、自分の思いを堂々と伝えてください。
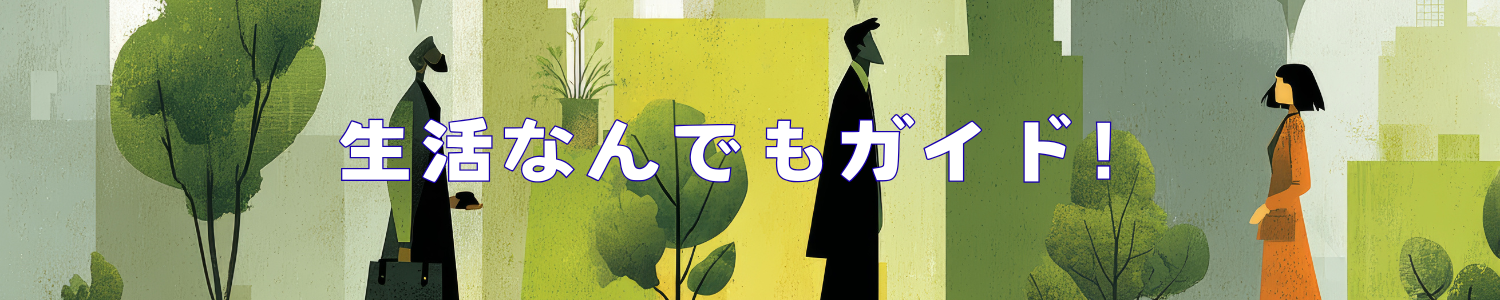
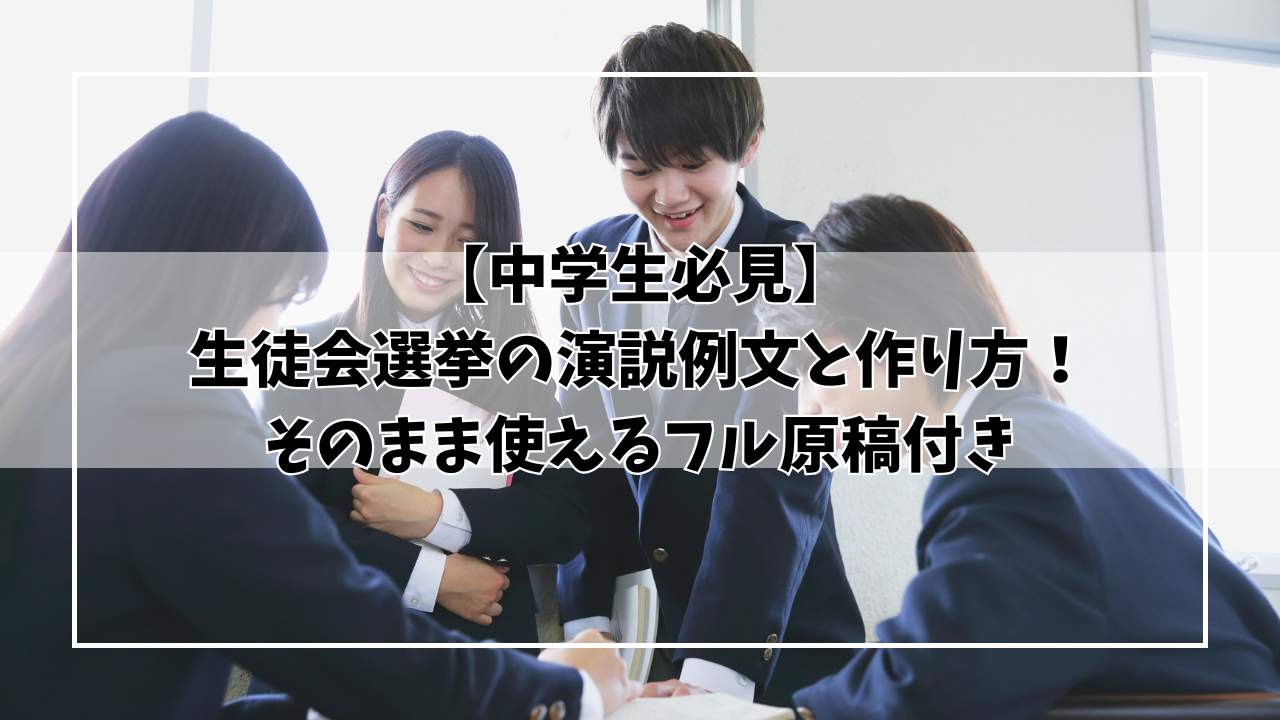
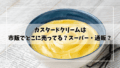
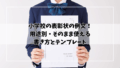
コメント